

下仁田町は古くから、ネギとコンニャクの名産地として知られています。独特の土壌や地形はネギとコンニャクの栽培に適しています。傾斜のある山から流れる川は強い水流を生み、水車を回す事でコンニャクの精粉に役立ちました。また、加熱することで甘くなる下仁田ネギはこの土地の土壌、気象環境で農家が15ヶ月かけて育て上げる大地の恵みです。

荒船風穴は崖崩れの岩塊の上に石を積んだ累積風穴と呼ばれるものです。荒船風穴は蚕の卵を冷蔵保護する場として明治38年から営業を開始しました。風穴の果たした役割は大きく、蚕の卵を低温保存することにより孵化の時期を調整することができ、年に複数回の養蚕を可能にしました。そしてこれが、繭、生糸の生産量を大きく伸ばしました。

跡倉クリッペは青岩と呼ばれる緑色の岩の上に、他所で形成した地層が覆いかぶさっています。クリッペを構成する地層は他所の場所で形成し、その後地殻変動で移動してきて、浸食されて山の上に部分的に孤立して残っているのです。町内にはダイナミックな地殻変動で動いてきた地層が変形した様子が見られます。

鏑川、南牧川の合流地点にある公園です。公園では16種の石が拾えますが、名前の由来となった青岩と呼ばれる緑色岩が特徴的です。緑色の平行な筋があります。この岩石は海底火山の噴出物や海底の砂泥が地下深くに移動した際、強い圧力を受ける事によりできます。

クリッペが動いてきた岩石と基盤の岩石の境目が観察できます。岩石の境目ではクリッペが移動する時に岩盤が擦れ合い基盤の岩石は粘土化しています。この粘土が研磨剤のような役割をし、岩を磨くので岩の表面はつるつるとしていて、光沢があります。

ここでは、大きな力を受けて地層が上下さかさまになっているところと、正常に堆積しているところの両方をみることができます。逆転した部分では、当時の海底面にできた生物の巣穴や這い跡、水の流れによって削られた跡を見ることができます。

高さ25mもある蒔田不動の滝は、クリッペを構成する地層のひとつ2億7千万年前の石英閃緑岩でできています。石英閃緑岩は周りの地層に比べて固いため滝を作っています。
この川の上流にも、跡倉クリッペのすべり面が見られます。

日本三大奇勝の一つ妙義山は、周辺の丘陵地帯に突然屏風のような壁がそり立つような山で山肌がごつごつしているのが特徴です。この妙義山は、600万年前に活動した火山から噴き出た火山噴出物が長い年月雨風に削られることで現在のようなかたちになりました。



山頂が平らな山「荒船山」。それがまるで荒れた海に浮かぶ船のように見えることからこの名前がつきました。なぜ平坦なのか?それは700万年前の火山活動で地面に平らに流れた「荒船溶岩」が残ったものだと考えられています。荒船山登山道では「荒船溶岩」が流れるまでの火山活動のストーリーを垣間見ることができます。


地すべり地形を利用した日本最古の洋式牧場です。ジャージー牛を多く飼育しており、乳製品などの商品が人気を集めています。

この断層は「大北野―岩山断層」と呼ばれており、西は九州まで伸びている大断層「中央構造線」の一部です。下仁田町は、関東で最もよく「中央構造線」が見られます。

奥栗山渓谷は下仁田町の最高峰「白髪岩」から流れる栗山川が、1億年前の深海底に降り積もってできたチャートを削って深い渓谷を作っています。渓谷内には「三段の滝」「昇龍の滝」と呼ばれる滝なども巡れる散策コースが整備されています。色とりどりのチャートを河川が削って、美しい景観を織りなしているのです。


甘楽富岡を代表する標高1370Mの独立峰です。東西に尾根を連ねる。中腹から山頂にかけて風化侵食に強いチャートが多く、断崖の多い険しい山になっています。山頂からは360度見渡すことができ、気象条件によりスカイツリーが見えます。

ジオパーク名:下仁田ジオパーク
ジオパーク名(英語表記):Shimonita Geopark
団体名:ジオパーク下仁田協議会
構成自治体名:群馬県下仁田町
■ジオパーク下仁田協議会事務局
〒370-2611 群馬県甘楽郡下仁田町大字青倉158-1 下仁田町自然史館内
TEL 0274-70-3070 Fax 0274-67-5315
■E-mail 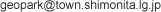
■ウェブサイト 下仁田ジオパーク